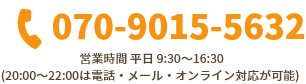精神疾患の方で障害年金をもらえない人・不支給になってしまう理由とその対策
障害年金とは
障害年金とは、病気やケガにより働くことが困難な方に対して、一定の条件を満たすことで支給される公的な年金制度です。国民年金や厚生年金に加入している方が、障害状態に至った場合に生活を支えるための経済的支援を目的としています。障害年金は、その障害の程度に応じて受給額が異なり、1級、2級、3級といった区分で決定されます。
障害年金受給の必須条件
障害年金を受給するには、以下の3つの条件を満たす必要があります。
初診日要件
障害年金の申請において「初診日」とは、障害の原因となった病気やケガで初めて医療機関を受診した日を指します。この初診日を特定できなければ、障害年金を申請することはできません。初診日は、受給資格を判断する上で非常に重要な基準となりますが、その証明が困難なこともあります。
例えば、医療機関の記録や診療明細書、カルテの写しなどをもとに初診日を証明することが求められます。よって、当時の通院先が閉院している場合は、他の医療機関の紹介状や第三者の証言を活用することも有効です。こうしたポイントを押さえて、初診日を確実に証明することが重要です。
保険料納付要件
障害年金を受給するためには、年金保険料を一定期間納付している必要があります。
具体的には、初診日のある月の前々月時点での公的年金の加入期間の2/3以上が納付または免除されていること、もしくは直近1年間に未納がないことが条件です。納付要件を満たしていないと、不支給となります。
障害認定日要件
「障害認定日」とは、初診日から1年6か月を経過した日、またはその間に治癒した日を指します。障害認定日における障害の程度が年金の受給基準に該当しているかどうかが、受給可否の判断に大きく影響します。障害認定日において、障害状態が一定等級以上で認定される必要があります。
精神疾患で障害年金が不支給になってしまう理由
申請におけるよくある失敗事例
精神疾患や発達障害で障害年金の申請を行った場合でも、不支給になることがあります。以下では、不支給の主な理由について解説します。
診断書に記載された日常生活の支援内容と、申立書の生活記録が一致していない
障害年金の審査において、診断書と病歴・就労状況等申立書の内容の一致は非常に重要です。特に、診断書に記載された日常生活における支障と、申立書に記載された生活状況が一致していない場合、不支給となるリスクが高まります。
例えば、診断書には「日常生活において大きな支援が必要」と記載されているのに、申立書には「自立して生活している」といった矛盾があると、審査側にとって信頼性を欠くことになります。
病歴・就労状況等申立書の内容が薄い
病歴・就労状況等申立書には、これまでの病歴や現在の症状、日常生活の様子について具体的に記載することが求められます。この内容が不十分であったり、詳細に記載されていない場合、障害の程度が審査側に正確に伝わらず、不支給の判断を下されることがあります。申立書には、自分の状況を可能な限り具体的に、例えば「食事の準備にどれくらいの支援が必要か」「通院の際にどのような助けが必要か」など詳細に記載することが重要です。
医師が書いた診断書を確認せずに、そのまま提出してしまっている
診断書は障害年金の申請において最も重要な書類の一つです。しかし、医師が作成した診断書の内容を確認せず、そのまま提出してしまうと、内容に誤りや不足がある場合、不支給の原因となります。診断書には、障害の程度や日常生活での支障について詳細に記載されている必要があります。申請者自身が診断書を確認し、必要に応じて医師に修正を依頼することが大切です。
働いていると障害年金はもらえない?
精神疾患の方が働いている場合、「働いていると障害年金がもらえないのでは?」という疑問を抱く方も多いでしょう。
精神疾患は内部疾患であるため、数値などで等級が明確に示されるものではないため、「就労状況の考慮」が判定の判断の一つとなります。
具体的には、下記のことを細かく病歴・就労状況等申立書に記載するように心がけてください。
・仕事の内容
・仕事をしている1日の時間
・仕事をしている1週間の日数
・職場での配慮や援助(例:仕事内容に配慮があり取り組みやすい作業をしている)
・仕事における困難な点(例:障がいによるコミュニケーションの難しさ)
不支給になった場合の注意点と対応策
障害年金の申請が不支給となった場合でも、諦めずに次の対応を取ることが重要です。
審査請求・再請求について
不支給の決定に対して異議がある場合、「審査請求」を行うことができます。審査請求とは、不支給の決定に対して再評価を求める手続きで、決定通知を受け取った日から3か月以内に行う必要があります。審査請求においては、不支給の理由を把握し、診断書の内容を修正するなど、適切な対応を取ることが大切です。
また、審査請求が認められなかった場合でも、再度申請(再請求)を行うことが可能です。不支給の原因を分析し、必要な情報を追加したり、書類を改善したりすることで、再請求の成功率を高めることが期待できます。専門家である社会保険労務士に相談することで、手続きをスムーズに進めることができ、受給の可能性も高まります。
まとめ
精神疾患による障害年金の申請において、不支給となる理由はさまざまです。しかし、申請に必要な条件を満たし、必要な書類を適切に準備することで、受給の可能性を高めることができます。不支給となった場合でも、諦めずに審査請求や再請求を行い、専門家のサポートを受けることで、再度の申請が成功する可能性は十分にあります。
例えば、以前に初診日の証明が不十分だった方が、第三者の証言を用いて証明を強化し、再請求で受給に成功した事例があります。また、病歴・就労状況等申立書の内容を具体的に改善したことで、不支給から受給へとつながったケースもあります。
障害年金の受給に不安がある方は、ぜひ社会保険労務士に相談して、適切なアドバイスを受けることをお勧めします。まずは、自身の状況を正確に把握し、必要な書類を整えることから始めてみてください。
最終更新日 1か月 ago
投稿者プロフィール

- Ray社労士オフィス 代表 社会保険労務士
-
私には身体障害者手帳と療育手帳を持つ子どもがおり、障害者手帳を受け取った際の悩みや不安、孤独感を今でも鮮明に覚えています。
複雑な日本の社会保障制度の中でも、特に専門性を必要とするのが障害年金です。
この経験と社会保険労務士としての知識や経験を活かし、「同じ悩みを抱える方々の一筋の光となりたい」という強い想いのもと、Ray社労士オフィスを立ち上げました。
障害年金申請のサポートはもちろん、皆様の言葉に耳を傾け、心配事や将来の不安を解消し、安心して暮らせる明日を築くお手伝いをいたします。どうぞお気軽にご相談ください。
最新の投稿
- 10月 11, 2025面談コラム働ける脳出血でも障害年金は対象?|小脳出血による麻痺での相談事例(厚生年金加入中)
- 9月 23, 2025面談コラム潰瘍性大腸炎で障害年金はもらえる?|50代男性の相談事例(障害厚生年金3級の可能性)
- 8月 25, 2025面談コラム【特発性大腿骨頭壊死で歩行困難】人工関節の手術後も悪化した方からのご相談(石川県)
- 8月 18, 2025面談コラム【障害年金】脳出血による左半身に麻痺が残ってしまった方からのご相談(石川県金沢市)
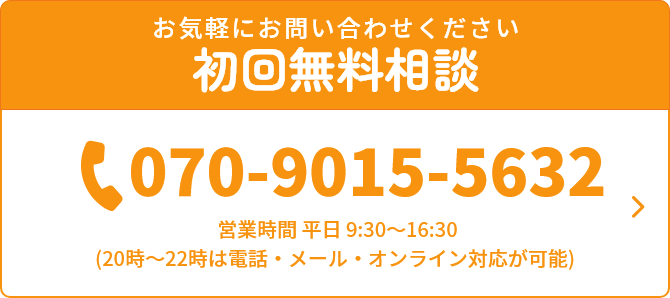


 初めての方へ
初めての方へ