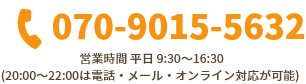障害年金は自分で申請できる?
障害年金の申請は、基本的には誰でも自分で行うことができます。しかし、多くの人にとって、その手続きの複雑さや労力の多さは大きなハードルとなっています。実際、厚生労働省の2023年調査によると、障害年金の申請手続きの約30%が書類不備や手続きの遅延により失敗しているというデータがあります(出典:厚生労働省「障害年金に関する実態調査」)。このような背景から、多くの人が申請を途中で諦めてしまうのが現状です。この記事では、障害年金の申請を自分で行う際に直面する手間やデメリットについて詳しく説明し、それらを克服するための具体的な対策も合わせてご紹介します。
行政手続きと専門家のサポート
行政手続きの多くは個人で行うことが可能ですが、障害年金の申請は専門家に頼ることで成功率が高まることが多いです。
障害年金の申請手続きは、他の行政手続きと同様に個人で行うことが可能です。
しかし、裁判を弁護士に依頼する方が多いです。それは、法律の専門知識や手続きの複雑さから個人での対応が難しいように、障害年金の申請も専門的な知識や複数の書類の整備が求められます。例えば、申請には初診日の証明や診断書、病歴・就労状況等申立書など、各書類の正確な記載が不可欠です。また、審査基準に沿った形で情報を整える必要があり、これを誤ると不支給のリスクが高まります。こうした理由から、専門家である社会保険労務士に依頼することが安心につながるのです。障害年金には審査があり、支給されるかどうかが分かれるため、支給という結果を目指すためには、専門家に依頼する方が安心です。
障害年金の申請は非常に複雑であり、社会保険労務士に依頼することで成功への道が開けます。具体的には、以下のようなメリットがあります。
まず、社労士は審査基準を熟知しており、必要な書類の準備や記入方法について適切なアドバイスが受けられます。
例えば、実際に過去の事例で、申請者が書類の不備で一度は不支給になったケースにおいて、社労士が関与することで書類の改善が行われ、再申請で無事に受給が認められたことがあります。
このケースでは、診断書の内容に不備があり、日常生活での支障が十分に説明されていませんでした。社労士は申請者と医師の間に入り、具体的にどのような情報を記載すべきかを医師に伝え、診断書を修正しました。また、病歴・就労状況等申立書の記載内容についても、より詳細に障害が生活に与える影響を補足し、審査基準に沿った内容に整えることで、再申請が成功しました。また、初診日や診断書などの重要書類の取り扱いについても、社労士のサポートがあれば不備を防ぎ、より正確かつ効率的に進めることができます。さらに、社労士の経験に基づくアドバイスにより、審査基準に沿った最適な対応が可能です。さらに、社労士に依頼することで心理的な負担が軽減され、より安心して手続きを進めることが可能です。
制度が難しい問題
障害年金の申請制度は、多くの人にとって分かりにくく、複雑な構造をしています。どのような書類が必要か、どの基準で審査されるのか、といった情報を正確に理解し、適切な対策をとることが求められます。例えば、障害年金の審査では、初診日の証明、障害状態を示す診断書、これまでの治療や就労の経歴(病歴・就労状況等申立書)が必要です。
審査基準としては、障害の程度や日常生活への支障の度合いが重視されます。例えば、食事の準備や摂取が自力でできるか、入浴やトイレの使用に支援が必要かといった具体的な行動が評価されます。これらの日常生活の動作がどの程度制限されているかが、受給の可否に大きく影響します。特に、診断書には障害の影響が日常生活にどのように及んでいるかを詳細に記載する必要があり、これが不十分だと不支給となるリスクがあります。そのため、多くの方は次のような問題に直面します。
障害年金の申請では、診断書の内容が非常に重要であり、これが適切に記載されていなければ申請が通らないことがあります。申請者自身が診断書の内容を完全に理解し、医師に適切な指示を出すことは難しく、結果として書類に不備が生じ、申請が通らないケースが多く発生しています。また、必要書類の取得や各種説明書の読み込みに多大な時間と労力がかかり、申請の途中で諦めてしまう人も少なくありません。
その他、医師との詳細なコミュニケーションが求められる点も難しい部分です。医師に診断書を正確に記載してもらうためには、具体的な障害の影響や日常生活の困難さを正確に伝える必要があります。これらの手続きは非常に煩雑であり、初めて取り組む方にとっては混乱しやすく、途中で諦めてしまうことも少なくありません。
年金事務所で手続きをすればいいのでは?
「社会保険労務士に頼まなくても、年金事務所で相談すればよいのでは?」と考える方も多いと思います。
年金事務所で手続きをすることも可能ですが、年金事務所の職員は障害年金の審査に関して専門的な知識を持っているとは限りません。なぜなら、年金事務所の業務は年金全般にわたる広範な内容を扱っており、障害年金の相談はその一部に過ぎないからです。そのため、年金事務所での対応が必ずしも申請者にとって最適とは言えない場合があります。
また、年金事務所の職員は、公平公正な対応が求められており、個々の相談者にとって最も有利になるような具体的なアドバイスを提供することが難しい状況にあります。例えば、「どうすれば障害年金を受給できますか?」という質問に対しても、「このようにすれば受給できます」という具体的なアドバイスは提供されません。その代わりに、「申請をしていただかないと結果については何とも言えません」といった回答になることが一般的です。
そのため、障害年金の申請においては、専門知識と経験を持った社会保険労務士に依頼することが、より確実な受給につながるため有効です。社労士は、申請者に寄り添いながら、必要な手続きを適切にサポートし、受給の可能性を最大限に高めるための具体的な助言を行います。
社会保険労務士の選び方
こうした手続きの煩雑さや専門的な知識の必要性から、社会保険労務士(社労士)に依頼することを検討する方が多くいます。特に、審査請求や再審査請求まで対応してくれる社労士を選ぶことが、結果的に受給成功の可能性を高める重要な要素となります。審査請求は、不支給の決定に対して異議を申し立てる手続きであり、再審査請求はさらにその決定に対して再度の異議を申し立てる手続きです。これらの手続きには、非常に複雑な書類作成と法的な知識が必要です。社労士は、不支給理由を詳細に分析し、どのように改善すれば受給が認められる可能性があるかを判断し、必要な書類の修正や追加証拠の準備をサポートします。こうした専門的なサポートを受けることで、申請者は不安を軽減し、より確実に受給に向けたプロセスを進めることができます。
社労士を選ぶ際には、以下の具体的なチェックリストに注目すると良いでしょう。例えば、過去に社労士に依頼したことで成功した事例として、初診日の証明が困難だったケースにおいて、社労士が適切な証拠を集め、無事に受給に至ったという体験談があります。また、受給実績を確認する際には、実際にサポートを受けた人からの具体的なフィードバックを参考にすることで、信頼性をより確実に判断することができます。
- 経験豊富な社労士を選ぶ:障害年金の申請には専門的な知識が求められます。特に、同様のケースを扱った経験のある社労士であれば、安心して手続きを任せることができます。
- 受給実績を確認する:過去の受給実績やクライアントの声を確認することで、その社労士の信頼性を判断する材料になります。
- 対応の丁寧さとコミュニケーション能力:申請プロセス中に何度もやり取りが発生するため、対応が丁寧で質問に対してわかりやすく答えてくれる社労士を選ぶことが重要です。
- 料金体系の明確さ:社労士に依頼する際の費用について、事前に明確な料金体系を確認することが大切です。追加費用が発生する場合の条件も含めて、契約前に確認しておきましょう。
- 相談のしやすさ:初回の相談時に、相談しやすい雰囲気を感じられるかも大切です。申請プロセスは長期間にわたるため、信頼して相談できる相手かどうかを見極めましょう。
自分で申請して不支給処分を受けた場合
自分で申請を行い、不支給処分を受けた場合でも、再度の申請や不服申立ての手段があります。しかし、不支給の理由を理解し、適切に対応するためには、専門的な助言が必要となることが多いです。しかし、これらの手続きはさらに複雑であり、専門知識がないと再申請の成功率が低くなる傾向があります。そのため、不支給処分を受けた場合は、速やかに社労士に相談し、サポートを受けることが推奨されます。
まとめ
障害年金は自分で申請することが可能ですが、その過程で直面する手間や専門的な知識の必要性から、多くの人が途中で挫折するリスクがあります。まずは信頼できる社労士に相談し、手続き全体の見通しを立てることが重要です。専門家に依頼することで、複雑なプロセスを効率的に進めることができ、結果的に申請成功の可能性を高めることができます。特に、初診日の証明や診断書の内容の適切な記載など、重要なポイントでの失敗は受給権を失う原因となり得ます。こうしたリスクを回避するためには、経験豊富な社労士に依頼することが有効です。社労士に依頼することで、申請プロセスを円滑に進め、不安を軽減しながら受給に向けた取り組みを進めることができます。
最終更新日 1年 ago
投稿者プロフィール

- Ray社労士オフィス 代表 社会保険労務士
-
私には身体障害者手帳と療育手帳を持つ子どもがおり、障害者手帳を受け取った際の悩みや不安、孤独感を今でも鮮明に覚えています。
複雑な日本の社会保障制度の中でも、特に専門性を必要とするのが障害年金です。
この経験と社会保険労務士としての知識や経験を活かし、「同じ悩みを抱える方々の一筋の光となりたい」という強い想いのもと、Ray社労士オフィスを立ち上げました。
障害年金申請のサポートはもちろん、皆様の言葉に耳を傾け、心配事や将来の不安を解消し、安心して暮らせる明日を築くお手伝いをいたします。どうぞお気軽にご相談ください。
最新の投稿
- 10月 11, 2025面談コラム働ける脳出血でも障害年金は対象?|小脳出血による麻痺での相談事例(厚生年金加入中)
- 9月 23, 2025面談コラム潰瘍性大腸炎で障害年金はもらえる?|50代男性の相談事例(障害厚生年金3級の可能性)
- 8月 25, 2025面談コラム【特発性大腿骨頭壊死で歩行困難】人工関節の手術後も悪化した方からのご相談(石川県)
- 8月 18, 2025面談コラム【障害年金】脳出血による左半身に麻痺が残ってしまった方からのご相談(石川県金沢市)
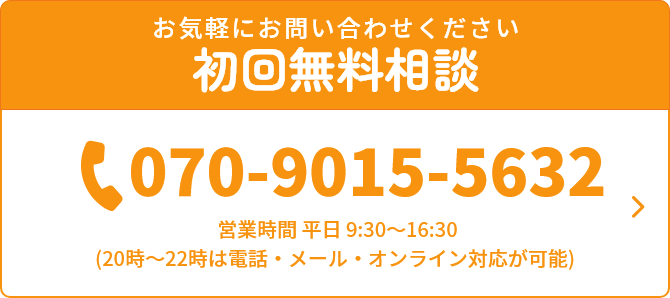


 初めての方へ
初めての方へ