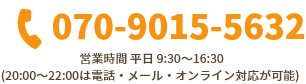【専門家が解説】障害共済(厚生)年金とは?申請時のポイントを解説!
目次
障害年金制度は、病気やけがによって日常生活や就労に制限を受ける方に対して、経済的な支援を提供する制度です。本記事では、特に「障害共済年金」および「障害厚生年金」について、その概要から申請のポイント、受給の流れなどを詳しく解説していきます。
障害共済(厚生)年金とは?
障害共済年金とは共済組合に加入中に初診日がある公務員や教職員などの方が、初診日の病気やけがにより障害状態となった場合に支給される年金です。これに対して障害厚生年金は、厚生年金保険に加入中に初診日がある会社員の方などが対象となります。
ただし、この区分は平成27年10月1日に共済年金と厚生年金の一元化が行われたため、受給権発生日が一元化後にある場合は、名称も障害厚生年金に統一されることとなりました。
これまで、障害共済年金と障害厚生年金では制度的な取り扱いで異なる点が多くありましたが、一元化後は制度間における差を解消して、基本的な取扱いを障害厚生年金に合わせる方針となりました。
障害共済年金の受給条件について
障害共済年金の受給にはいくつかの要件があります。主に以下の3つの条件を満たす必要があります。
- 初診日要件:病気やけがの初診日が共済年金に加入している期間中であること。
- 保険料納付要件:初診日がある月の前々月において、保険料納付済期間が全体の3分の2以上であること。また、直近1年間に未納がないことも必要です。
- 障害状態該当要件:初診日から1年6か月経過後に障害等級(1級から3級)に該当する状態であること。
これらの要件をすべて満たした場合に、障害共済年金の受給資格が得られます。
障害共済年金のもらえる金額(2024年度)
障害共済年金の支給額は、加入期間や給与の水準によって異なります。一般的に、障害共済年金の金額は厚生年金よりも高めに設定されていることが多く、次の合算額が支給されます。
基礎年金 + 厚生年金相当額 + 職域年金相当部分 + (加給年金額)
また、障害等級が1級、2級、3級のどれに該当するかによっても支給額は変動します。
障害基礎年金について
障害の程度が1級または2級に該当したときは、原則として国民年金の「障害基礎年金」があわせて支給されます。
ただし、障害の程度が3級のときは、障害共済年金のみが支給されます。
障害基礎年金の額
1級 972,250円
2級 777,800円
加給年金額
加給年金額は234,800円です。
障害の程度が1級または2級の障害共済年金について、その方によって生計を維持されている65歳未満の配偶者(事実婚を含む)がいるときに加算されます。
なお、障害共済年金の受給権が発生した時点で配偶者がいなくても、その後婚姻等をした場合は、別途届け出は必要ですが、加算されます。
また、加給年金額は、配偶者が退職共済年金(組合員期間が20年以上のものか、20年以上あるものとみなされるものに限ります)、障害共済年金、その他公的年金の退職(老齢)または障害を給付事由とする年金を受けているときは支給が停止されます。
子の加算額
障害基礎年金の額には、その方によって生計を維持されている18歳の年度末(一般的に高校卒業まで)の子、または20歳未満で障害の程度が1級、2級に該当している子がいるときは、次の加算額が加算されます。
なお、配偶者の加算と同様に、障害基礎年金の受給権が発生した時点で、加算額の対象となる子がいなくても、その後、出生等により加算の要件を満たすことになった場合は、届け出を行うことで加算されます。
子の人数
2人目まで1人につき 234,800円
3人目から1人につき 78,300円
共済組合の種類
障害共済年金を受給するためには、どの共済組合に加入していたかも重要です。共済組合は、公務員、教職員、地方自治体職員など、職種によって異なります。以下は代表的な共済組合の例です。
- 国家公務員
- 国家公務員共済組合連合会
- JR・NTT・JTで平成9年までに退職した方、それ以降は厚生年金
- 日本郵政グループ
- 地方公務員
- 教員公立学校共済組合
- 警察共済組合
- 道府県職員:地方職員共済組合
- 市町村職員:市町村職員組合
- 東京都職員:東京都職員共済組合
- 政令指定都市職員:各都市の共済組合(または市町村共済組合)
- 健保組合がある都市職員:共済組合
- 私立学校の教職員
- 日本私立学校振興・共済事業団
それぞれの共済組合によって申請手続きや必要書類が異なる場合があります。
また、申請先はそれぞれ加入していた共済組合に申請をする必要があり、それは退職後であっても変わりません。ご自身がどの共済組合に属しているかを確認しておくことが大切です。
申請方法と必要書類
障害厚生年金や障害共済年金を申請する際には、以下の書類が必要です。
- 年金請求書
- 診断書(指定様式):医師による障害状態の診断を記載したもの
- 受診状況等証明書:初診日を証明するための書類
- 病歴・就労状況等申立書:発症から初診日までの経過や現在までの受診状況、就労状況などを記載する書類
申請にあたっては、これらの書類を揃えて共済組合の窓口に提出する必要があります。
ただし、独自の申請書類や別途書類が必要になる場合もあります。手続きが煩雑なため、専門家(社労士)に相談することも検討すると良いでしょう。
請求の流れ
障害共済年金の請求は、以下の手順で行います。
- 初診日の特定と証明:まず、初診日を証明する書類を取得します。
- 診断書の取得:主治医に依頼して、障害年金用の診断書を作成してもらいます。
- 必要書類の準備:共済組合に問い合わせをして、必要書類(診断書、請求書など)を確認。所定の様式がある場合は取り寄せておきましょう。
- 申請書類の作成・提出:必要書類を揃えて、共済組合に書類を提出します。
- 審査:提出された書類をもとに審査が行われ、受給の可否が決定されます。
- 年金の決定:提出した書類をもとに、共済組合において障害共済年金の決定及び年金証書の送付がなされます(おおむね3か月程度)
共済組合の審査は厳しいの?甘いの?
障害共済年金は、障害厚生年金や障害基礎年金と比べて認定が甘い・緩いという感覚は、障害年金申請事業を行っている他の社労士からもよく聞きます。
その他、障害厚生年金や障害基礎年金より等級が高くなるケースも多いです。
さらには、初診日が証明できない場合でも、自己申告で認定されていた過去がありました。
これらは厚生年金の一元化後は、官民格差が激しいとのことで、改善した点もありますが、やはり現状もやや認定が緩いことがあります。
障害共済年金は受給に至りやすいですが、デメリットとして、書類の用意が通常より複雑で大変という点があります。(組合によって変わります)
まとめ
障害厚生年金や障害共済年金は、病気やけがで生活が困難になった際に大きな支えとなる制度です。しかし、申請には多くの書類や手続きが必要で、審査も厳しいため、事前にしっかりと準備を行うことが大切です。もし申請に不安がある場合や手続きに困難を感じる場合は、専門家である社会保険労務士に相談することをお勧めします。
私たちの事務所では、障害年金の申請に関するご相談を受け付けております。初診日の特定や診断書の準備など、手続き全般をサポートいたしますので、お気軽にお問い合わせください。
最終更新日 1か月 ago
投稿者プロフィール

- Ray社労士オフィス 代表 社会保険労務士
-
私には身体障害者手帳と療育手帳を持つ子どもがおり、障害者手帳を受け取った際の悩みや不安、孤独感を今でも鮮明に覚えています。
複雑な日本の社会保障制度の中でも、特に専門性を必要とするのが障害年金です。
この経験と社会保険労務士としての知識や経験を活かし、「同じ悩みを抱える方々の一筋の光となりたい」という強い想いのもと、Ray社労士オフィスを立ち上げました。
障害年金申請のサポートはもちろん、皆様の言葉に耳を傾け、心配事や将来の不安を解消し、安心して暮らせる明日を築くお手伝いをいたします。どうぞお気軽にご相談ください。
最新の投稿
- 10月 11, 2025面談コラム働ける脳出血でも障害年金は対象?|小脳出血による麻痺での相談事例(厚生年金加入中)
- 9月 23, 2025面談コラム潰瘍性大腸炎で障害年金はもらえる?|50代男性の相談事例(障害厚生年金3級の可能性)
- 8月 25, 2025面談コラム【特発性大腿骨頭壊死で歩行困難】人工関節の手術後も悪化した方からのご相談(石川県)
- 8月 18, 2025面談コラム【障害年金】脳出血による左半身に麻痺が残ってしまった方からのご相談(石川県金沢市)
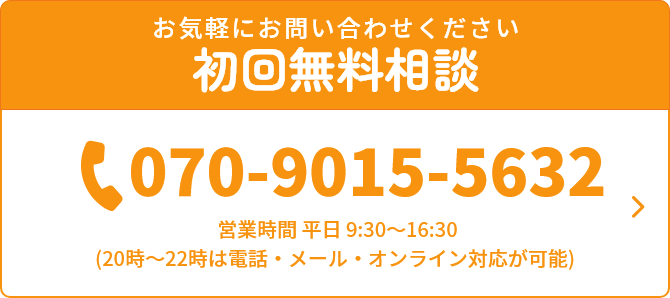


 初めての方へ
初めての方へ