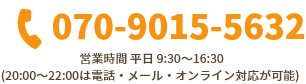【社労士が解説】障害年金をもらえない人の条件とは
障害年金は、障害を持つ方々にとって経済的な支えとなる重要な制度です。例えば、突然の病気や事故によって就労が困難になった場合でも、障害年金は生活を支える大きな助けとなります。しかし、全ての障害を持つ人が必ずしも受給できるわけではありません。受給にはさまざまな要件があり、その要件を満たさない場合は支給が認められないことがあります。この記事では、障害年金を受給できないケースについて専門的な視点から詳しく解説します。
障害年金とは?
障害年金とは、病気やけがによって生活や就労に制限が生じた際に、経済的な支援を提供する公的年金制度です。障害基礎年金と障害厚生年金があり、初診日に加入している年金制度に応じて支給内容が異なります。
障害年金は、国民年金または厚生年金に加入している方が、病気やけがによって日常生活や就労に大きな制約を受ける場合に支給される年金です。障害の程度に応じて、1級から3級までの障害等級が設定されており、それに応じた金額が支給されます。また、初診日や保険料の納付状況など、受給するためにはいくつかの要件を満たす必要があります。
障害年金をもらえない人とは?
障害年金はすべての人に支給されるわけではありません。以下の条件に該当する場合、障害年金を受給できないことがあります。
保険料の納付要件を満たしていない
障害年金の受給には、保険料の納付が必要です。初診日前に一定期間の保険料を納付していない場合、受給資格を失います。
具体的には、初診日の前日において、初診日がある月の前々月までの保険料納付期間が全被保険者期間の3分の2以上である必要があります。
また、特例として、初診日の前日において、初診日がある月の前々月までの直近1年間に未納がないことでも要件を満たす場合があります。
初診日が特定できない
障害年金の申請には、病気やけがの初診日が重要な要素となります。初診日を証明するためには医師がカルテに基づいて作成する『診断書』 または 『受診状況等証明書』が必要です。
ですが、初診日から10年も経過しているなどの理由で、カルテが廃棄されていたり、病院自体が廃院していたりして、初診日の証明がとれない場合があります。その場合は、障害年金をもらえない理由となります。
ただし、この場合でも、障害年金をもらえる可能性はあります。参考資料を用意できたり第三者の証明ができる場合です。
詳しくはこちらの記事で解説しております。
病状が障害年金の等級に該当していない
障害年金は、障害の程度に応じて支給されますが、病状が障害等級に該当しない場合は受給できません。障害等級は、1級から3級までありますが、障害基礎年金には1級と2級、障害厚生年金には1級から3級に区分されています。
この等級は日常生活や就労にどの程度支障があるかで判断されます。判断基準はおおむね以下の通りです。
1級:日常生活に他人の介助が不可欠であって日常生活の活動または入院中の活動が自身のベッド周辺に限られている
2級:日常生活に著しい支障が生じている場合で軽作業はできるものの就労は出来ず日常の活動が家の中だけ、入院中の場合には病棟の中だけに限定されている
3級:労働に著しい支障が生じフルタイムで就労することが出来ず日常生活にも支障が生じている
※ただし、肢体の障害、人工関節、人工肛門、人工透析の場合などは、フルタイムで就労を行っている場合にも障害年金2~3級に該当します。
「20歳前傷病」で年収が一定以上ある人
20歳前に発症した傷病で障害年金を申請する場合、本人の年収が一定以上であると受給資格が制限されます。
具体的には、年収が約370万円以上ある場合は、支給停止となる可能性があります。これは、20歳前傷病による障害年金は年金の加入や年金保険料の納付を要件としていないためであり、高額な収入がある場合は経済的な支援が不要とみなされるためです。
具体的には次のように定められています。
・前年の所得額が4,721,000円を超える場合は年金の全額が支給停止
・前年の所得額が3,704,000円を超える場合は2分の1の年金額が支給停止
※扶養親族がいる場合は、扶養親族1人につき所得制限額が38万円加算されます。
(対象となる扶養親族が老人控除対象配偶者または老人扶養親族であるときは、1人につき48万円が加算され、特定扶養親族または控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る)であるときは1人につき63万円が加算されます)
20歳未満の人
障害年金は原則として20歳以上の人が対象です。そのため、20歳未満の場合は受給することができません。
ただし、例外として中学校や高校卒業後に働き始めて厚生年金に加入していた方が、20歳前の病気やケガで障害年金の等級に該当するようになった場合は障害年金を受給できる場合があります。
神経症の人
障害年金の対象となる精神疾患には、統合失調症やうつ病などがありますが、神経症(不安障害や適応障害など)は原則として対象外とされています。
ただし、神経症と別の疾患を併発している場合には、認定されることもあります。この場合に医師に診断書を書いてもらう際は、その旨を診断書の備考欄にICD-10コードを担当医に記載してもらうなどの注意点があります。
初診日から1年6か月が経過していない人
障害年金は、原則として初診日から1年6か月を経過した時点での障害状態が認定基準に該当する必要があります。このため、1年6か月未満の段階では受給が認められません。この間に症状が改善した場合は、障害年金の対象外となります。
ただし以下のような病気やケガは、1年6ヶ月を待たなくても良いケースがあります。これを「認定日特例」といいます。
・人工透析をしている人(人工透析開始から3ヶ月を経過した日)
・心臓ペースメーカー・人工弁を装着した人(装着した日)
・人工関節・人工肛門・人工膀胱を造設した人(造設した日)
・手足を切断した人(切断された日)
・脳梗塞、脳出血(初診日から6ヶ月以上経過し、医師が症状固定と判断した日)
障害年金の受給が困難なケース
65歳以上の人
初診日が65歳以上である場合、障害年金の申請は基本的にできません。ただし、すでに受給している場合は65歳以降も継続して受給することが可能です。また、老齢年金との選択制となり、どちらか有利な方を選ぶことが求められます。
医師が診断書を書いてくれない
障害年金の申請には、医師の診断書が必須です。しかし、医師が診断書を書いてくれない場合、申請が難しくなります。
診察の際に自分の症状を十分に伝えられなかったために、医師が障害年金の必要性を理解していなかったケースがあります。日頃から自身の生活の困難さを具体的に伝えることが重要です。
例えば、日常生活で具体的にどのような困難を抱えているのか、どのような支援が必要なのかを詳細に説明しましょう。就労している場合は、働く際に直面している具体的な困難や業務内容や勤務時間についても伝えることで、より適切な診断書を得ることができます。
障害年金をもらえないと諦めていた人
障害年金の申請を諦めていた人の中には、実際には受給資格があるにもかかわらず、情報不足や手続きの複雑さから申請を断念してしまったケースがあります。
このような場合、具体的な事例として、初診日を証明する書類が見つからない、またはどの書類が必要なのかが分からないといった問題が原因になることがよくあります。専門家のサポートを受けることで解決できる場合があります。社労士などの専門家に依頼することで、手続きがスムーズに進むだけでなく、受給の可能性も高まります。
まとめ
障害年金は、病気やけがで生活が困難な方々にとって重要な支援ですが、すべての人が受給できるわけではありません。保険料の納付状況や初診日の特定、医師の診断書の取得など、いくつかの条件を満たす必要があります。この記事を参考に、自分が受給資格を持つかどうかを確認し、不明点があれば専門家に相談することをお勧めします。
障害年金の申請手続きは非常に複雑で、専門的な知識が必要な場面も多いため、困ったときは迷わず社労士などの専門家に相談しましょう。特に、初診日の特定や診断書の取得に関してはサポートを受けることでスムーズに進められます。今すぐに行動を始め、必要な手続きを早めに進めることで、安心して生活を支える経済的な支援を得ることが可能です。私たちの事務所では、障害年金の申請に関するご相談を受け付けておりますので、ぜひお問い合わせください。
最終更新日 1年 ago
投稿者プロフィール

- Ray社労士オフィス 代表 社会保険労務士
-
私には身体障害者手帳と療育手帳を持つ子どもがおり、障害者手帳を受け取った際の悩みや不安、孤独感を今でも鮮明に覚えています。
複雑な日本の社会保障制度の中でも、特に専門性を必要とするのが障害年金です。
この経験と社会保険労務士としての知識や経験を活かし、「同じ悩みを抱える方々の一筋の光となりたい」という強い想いのもと、Ray社労士オフィスを立ち上げました。
障害年金申請のサポートはもちろん、皆様の言葉に耳を傾け、心配事や将来の不安を解消し、安心して暮らせる明日を築くお手伝いをいたします。どうぞお気軽にご相談ください。
最新の投稿
- 10月 11, 2025面談コラム働ける脳出血でも障害年金は対象?|小脳出血による麻痺での相談事例(厚生年金加入中)
- 9月 23, 2025面談コラム潰瘍性大腸炎で障害年金はもらえる?|50代男性の相談事例(障害厚生年金3級の可能性)
- 8月 25, 2025面談コラム【特発性大腿骨頭壊死で歩行困難】人工関節の手術後も悪化した方からのご相談(石川県)
- 8月 18, 2025面談コラム【障害年金】脳出血による左半身に麻痺が残ってしまった方からのご相談(石川県金沢市)
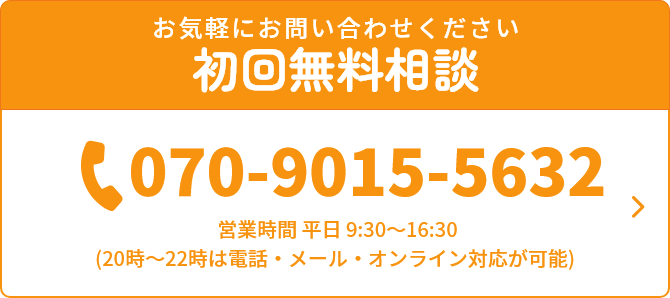


 初めての方へ
初めての方へ