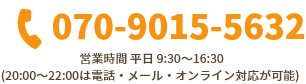障害年金の遡及請求とは?認定の可能性を高めるためのポイントと注意点
目次
障害年金の遡及請求とは?ポイントと注意点

遡及請求(そきゅうせいきゅう)とは?
遡及請求とは、障害認定日(原則として初診日から1年6ヶ月後の日)に、すでに障害等級に該当する状態だったにも関わらず、当時は請求しなかった方が、後からその時点にさかのぼって障害年金を請求する手続きのことです。
治療に専念していた、あるいは制度を知らなかったなどの理由で請求が遅れた場合でも、時効(5年)が完成していなければ、過去にさかのぼって年金を受け取れる可能性があります。
遡及請求のルールと「5年の時効」
遡及請求で最も重要なルールが「年金の支給を受ける権利は5年で時効になる」という点です。
例えば、障害認定日が10年前であっても、請求時点からさかのぼって受け取れる年金は最大で過去5年分となります。このルールを知らずに請求を先延ばしにすると、受け取れるはずの年金が時効によって月ごとに失われていくため、注意が必要です。
審査の結果、障害認定日時点の障害状態が等級に該当すると認められた場合、時効にかからない過去分の年金(最大5年分)が初回にまとめて支給されます。
遡及請求で認定の可能性を高めるためのポイント
遡及請求が認められるかどうかは、障害認定日当時のご自身の状態を、提出する書類でいかに客観的に証明できるかにかかっています。
-
障害認定日当時の診断書:最も重要な書類です。当時の症状や日常生活の状況が、障害等級に該当する水準であったことを示す必要があります。
-
病歴・就労状況等申立書:診断書を補足する重要な自己申告書類です。特に精神疾患の場合、日常生活や就労でどのような支障があったかを具体的に記述することが、審査においてご自身の状態を伝える上で大きなポイントとなります。
-
初診日の証明:遡及請求の前提として、初診日の証明は不可欠です。
これらの書類に整合性があり、障害認定日当時の状態が正確に反映されていることが、認定の可能性を高めることにつながります。就労していた方でも、当時の症状が重く、仕事に大きな支障が出ていたことを具体的に申し立てることで、認定を得られるケースは十分にあります。
申請が困難になりやすいケース
1. カルテが破棄されている 初診日から長期間経過していると、初診の医療機関でカルテが破棄されていることがあります(法律上の保存義務期間は5年)。初診日の証明ができないと、申請手続きを進めること自体が困難になります。 ただし、医療機関によっては電子カルテなどで長期間データを保存している場合や、2番目以降の病院のカルテ、お薬手帳など、他の資料で証明できる可能性もあります。
2. 障害認定日頃に通院していない 遡及請求の鍵となる「障害認定日当時の診断書」は、この時期のカルテを基に医師が作成します。そのため、障害認定日の前後で全く通院していない期間があると、医師も当時の状態を証明できず、診断書の作成が困難になります。 その結果、遡及請求が認められず、現在の症状だけで審査される「事後重症請求」での手続きとなる場合があります。
遡及請求が認められない場合とは?
障害認定日当時の診断書を提出できても、その内容が国が定める障害等級の基準に満たないと判断された場合は、遡及請求は認められません。 その場合でも、現在の症状が当時より重くなっていれば、「事後重症請求」として請求日以降の年金が認められる可能性があります。
受給できる年金額の目安
認められた場合、初回にまとまった金額が支給される可能性があります。
-
障害基礎年金2級:5年分の遡及が認められると、約400万円が一括で支給される場合があります。
-
障害厚生年金:お給料の額(報酬額)によって大きく変動しますが、数百万円から、場合によっては1,000万円を超えるケースもあります。
ただし、これはあくまで一例です。実際の金額は、認定される等級や個々の状況によって大きく異なります。
申請手続きを社会保険労務士に依頼するメリット
遡及請求は、通常の請求よりも証明すべき点が多く、手続きが複雑です。
-
初診日の証明が難しい
-
障害認定日当時の診断書を医師にどう依頼すれば良いか分からない
-
自分の症状を申立書でどう表現すれば伝わるか不安
このようなお悩みがある場合、年金手続きの専門家である社会保険労務士がサポートできます。私たちは、ご本人の状況を丁寧にお伺いし、認定の可能性を探りながら、必要な書類の準備や作成を的確に支援します。ご自身の状態を審査機関に適切に伝えるためのお手伝いをさせていただきます。
申請のご相談はお早めに
「もしかしたら自分も対象かもしれない」と思われたら、時効で受け取れる金額が減ってしまう前に、ぜひ一度ご相談ください。受給の可能性があるか、どのような準備が必要か、専門家の視点からアドバイスいたします。 ご相談だけでも歓迎ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。
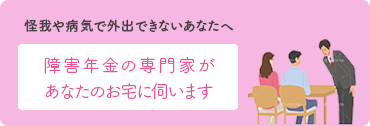
最終更新日 6か月 ago
投稿者プロフィール

- Ray社労士オフィス 代表 社会保険労務士
-
私には身体障害者手帳と療育手帳を持つ子どもがおり、障害者手帳を受け取った際の悩みや不安、孤独感を今でも鮮明に覚えています。
複雑な日本の社会保障制度の中でも、特に専門性を必要とするのが障害年金です。
この経験と社会保険労務士としての知識や経験を活かし、「同じ悩みを抱える方々の一筋の光となりたい」という強い想いのもと、Ray社労士オフィスを立ち上げました。
障害年金申請のサポートはもちろん、皆様の言葉に耳を傾け、心配事や将来の不安を解消し、安心して暮らせる明日を築くお手伝いをいたします。どうぞお気軽にご相談ください。
最新の投稿
- 10月 11, 2025面談コラム働ける脳出血でも障害年金は対象?|小脳出血による麻痺での相談事例(厚生年金加入中)
- 9月 23, 2025面談コラム潰瘍性大腸炎で障害年金はもらえる?|50代男性の相談事例(障害厚生年金3級の可能性)
- 8月 25, 2025面談コラム【特発性大腿骨頭壊死で歩行困難】人工関節の手術後も悪化した方からのご相談(石川県)
- 8月 18, 2025面談コラム【障害年金】脳出血による左半身に麻痺が残ってしまった方からのご相談(石川県金沢市)
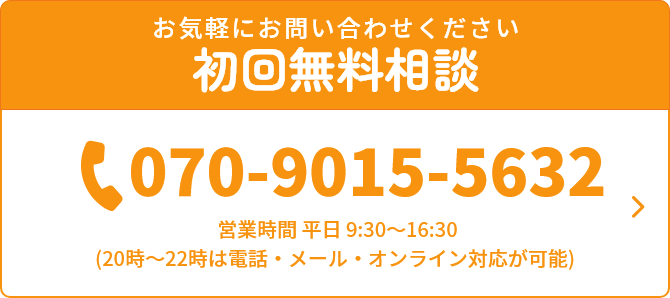


 初めての方へ
初めての方へ