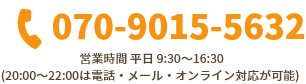【金沢】脳梗塞の障害年金申請|症状別に障害認定基準を紹介
目次
はじめに
脳梗塞は40代から50代の方に突然発症することが多い疾患で、働き盛りの方が急に就労困難な状態に陥るケースも少なくありません。金沢市をはじめとする石川県内においても、脳梗塞により後遺症を抱えながら生活されている方が数多くいらっしゃいます。
このような状況において、経済的な支援となるのが障害年金制度です。脳梗塞による後遺症は多岐にわたるため、症状に応じた適切な認定基準を理解することが重要です。本コラムでは、社会保険労務士として脳梗塞による障害年金申請について、症状別の認定基準から申請時の注意点まで詳しく解説いたします。
障害年金とは?
障害年金は、国民年金法および厚生年金保険法に基づく公的年金制度の一つです。病気やケガが原因で日常生活や就労に著しい制限を受ける場合に支給される年金で、老齢年金や遺族年金と同様に重要な社会保障制度です。
障害年金には以下の2種類があります:
障害基礎年金:初診日に国民年金に加入していた方が対象(自営業者、学生、無職の方など)
障害厚生年金:初診日に厚生年金に加入していた方が対象(会社員、公務員など)
脳梗塞の場合、初診日は緊急搬送された日となることが一般的です。初診日の年金加入状況により受給できる年金の種類が決定されるため、正確な初診日の確定が極めて重要です。
障害年金における3つの受給要件
障害年金を受給するためには、以下の3つの要件をすべて満たす必要があります。
初診日要件
初診日に原則として公的年金制度に加入していることが必要です。脳梗塞の場合、救急搬送された医療機関での受診日が初診日となります。ただし、20歳未満の方や60歳以上65歳未満で国内居住の方は、年金未加入でも対象となる場合があります。
保険料納付要件
以下のいずれかを満たす必要があります:
- 初診日の前日において、初診日のある月の前々月までの期間で、3分の2以上の期間について保険料を納付または免除されていること
- 初診日が令和8年4月1日前にある場合は、初診日において65歳未満で、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納期間がないこと
障害状態該当要件
障害の状態が、障害等級表に定める1級から3級までのいずれかに該当する必要があります。脳梗塞の場合、後遺症の種類と程度により等級が判定されます。
脳梗塞・脳出血の後遺症における障害認定基準
脳梗塞・脳出血による後遺症は多様であり、症状に応じて異なる障害認定基準が適用されます。
身体に麻痺が残る場合の障害認定基準
肢体の機能の障害の認定基準
脳梗塞により身体に麻痺が残る場合、「肢体の機能の障害」として認定されます。障害等級は以下の基準で判定されます。
1級:身体の機能の障害により、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度
- 他人の介助を受けなければほとんど自分の用事を済ませることができない状態
- 身のまわりのことはかろうじてできるが、それ以上の活動はできない状態
- 生活の範囲がベッド周辺に限られる状態
2級:身体の機能の障害により、日常生活が著しい制限を受ける程度
- 必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活が困難で労働により収入を得ることができない状態
- 簡単な家事(軽食作りや下着の洗濯等)はできるが、それ以上の活動はできない状態
- 活動範囲が家の中に限られる状態
3級:身体の機能に、労働が著しい制限を受ける程度の障害を有する状態
肢体の機能の障害の認定要領
認定要領では、日常生活における動作能力を具体的に評価します。評価項目は以下の通りです。
手指の機能
- つまむ(新聞紙が引き抜けない程度)
- 握る(丸めた週刊誌が引き抜けない程度)
- タオルを絞る(水をきれる程度)
- ひもを結ぶ
上肢の機能
- さじで食事をする
- 顔を洗う(顔に手のひらをつける)
- 用便の処置をする(ズボンの前後に手をやる)
- 上衣の着脱(かぶりシャツ、ワイシャツのボタン)
下肢の機能
- 片足で立つ
- 歩く(屋内・屋外)
- 立ち上がる
- 階段を上る・下りる
これらの項目は診断書において4段階で評価され、障害等級判定の重要な根拠となります。
そしゃく・嚥下能力に後遺症が残る場合の障害認定基準
脳梗塞により嚥下機能に障害が生じた場合、「そしゃく・嚥下機能の障害」として認定されます。
2級
- 流動食以外は摂取できない状態
- 経口的に食物を摂取することができない状態
- 経口的に食物摂取が極めて困難な状態
3級
- 経口摂取のみでは十分な栄養摂取ができないためゾンデ栄養の併用が必要な状態
- 全粥または軟菜以外は摂取できない程度の状態
後遺症として言語障害が残る場合の障害認定基準
脳の言語野に損傷を受けた場合、「音声または言語機能の障害」として認定されます。
構音障害または音声障害:発音に関わる機能の障害
失語症:大脳の言語野の後天性脳損傷により、いったん獲得された言語機能に生じた障害
2級
- 音声または言語機能を喪失した状態
- 話すことや聞いて理解することのいずれかまたは両方がほとんどできない状態
- 日常会話が誰とも成立しない状態
3級
- 音声または言語機能に著しい障害を有する状態
- 発声に関わる機能を喪失するか、話すことや聞いて理解することに著しい制限がある状態
後遺症として高次脳機能障害が残る場合
高次脳機能障害は、注意力・記憶力・言語・感情のコントロールなどの認知機能に生じる障害です。「精神の障害」の「症状性を含む器質性精神障害」として認定されます。
1級:高度の認知障害、高度の人格変化、その他の高度の精神神経症状が著明なため、常時の援助が必要な状態
2級:認知障害、人格変化、その他の精神神経症状が著明なため、日常生活が著しい制限を受ける状態
3級:認知障害のため、労働に著しい制限を受ける状態
高次脳機能障害の等級判定には、「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」も併せて考慮されます。
脳梗塞・脳出血の後遺症で障害年金を請求する際の注意点
障害認定日の特例を受けられるケースがある
通常、障害認定日は初診日から1年6ヶ月経過した日ですが、脳梗塞・脳出血の場合は特例があります。初診日から6ヶ月を経過した日以後に、医学的観点からそれ以上の機能回復がほとんど望めないと認められる場合は、1年6ヶ月を待たずに障害年金を請求できる可能性があります。
ただし、症状固定の判断は医学的観点から慎重に行う必要があるため、主治医との十分な相談が重要です。
後遺症の種類によって使用する診断書が異なる
脳梗塞・脳出血の後遺症に応じて、使用すべき診断書が以下のように異なります。
- 身体に麻痺が残る場合:「肢体の障害用の診断書」(様式第120号の3)
- そしゃく・嚥下・言語障害:「聴覚・鼻腔機能・平衡感覚・そしゃく・嚥下・言語機能の障害用の診断書」(様式第120号の2)
- 高次脳機能障害:「精神の障害用の診断書」(様式第120号の4)
複数の後遺症が併存している場合は、複数の診断書を提出することで併合認定により上位等級での認定を受けられる可能性があります。
主治医と、積極的にコミュニケーションを取る
診断書は障害年金請求における最重要書類です。短い診察時間では主治医が患者の日常生活の詳細を把握することは困難なため、以下の点を積極的に伝える必要があります。
- 日常生活のどの部分に不自由や不便を感じているか
- 家族からどのようなサポートを受けているか
- 具体的な症状や困難な動作
- 就労に関する制限や困難
主治医に作成してもらった診断書のチェック
主治医が作成した診断書は必ず内容を確認し、以下の点をチェックしてください。
- 日常生活の状況が現況に基づいて適切に表現されているか
- 症状が漏れなく記載されているか
- 実態よりも軽く記載されていないか
不適切な記載を発見した場合は、遠慮なく主治医に修正を依頼することが重要です。
病歴・就労状況等申立書を正しく記入する
病歴・就労状況等申立書は、診断書を補完する重要な書類です。以下の内容を具体的かつ客観的に記載します。
- 発病から初診までの経過
- その後の受診状況と治療経過
- 症状の変遷と現在の状態
- 日常生活における具体的な支障
- 就労状況と就労に関する制限
感情的な表現は避け、事実に基づいた客観的な記載を心がけることが重要です。
障害年金の申請手続きの流れ
障害年金の申請手続きは以下の流れで進みます。
STEP1:初回相談 年金事務所または市区町村の国民年金窓口で相談し、受給要件の確認と必要書類の説明を受けます。
STEP2:初診日の証明 受診状況等証明書により初診日を証明します。初診の医療機関が廃院している場合は、参考となる資料で立証します。
STEP3:診断書の作成依頼 症状に応じた診断書の作成を主治医に依頼します。障害認定日と現在の両方の診断書が必要な場合があります。
STEP4:病歴・就労状況等申立書の作成 発病から現在までの経過を時系列で詳細に記載します。
STEP5:その他必要書類の準備 年金加入期間確認通知書、住民票、戸籍謄本、年金手帳等を準備します。
STEP6:請求書類の提出 すべての書類を年金事務所に提出します。
STEP7:審査 日本年金機構において書類審査が行われます(標準的な審査期間は3ヶ月程度)。
STEP8:結果通知 年金証書または不支給決定通知書が送付されます。
まとめ
脳梗塞による障害年金申請は、後遺症の種類が多様であることから複雑な側面があります。適切な認定を受けるためには、症状に応じた障害認定基準の理解、適切な診断書の選択、医師との密接なコミュニケーション、そして正確な書類作成が不可欠です。
特に金沢市周辺にお住まいの方は、地域の医療機関や年金事務所との連携も重要になります。障害年金は生活を支える重要な制度ですが、申請には専門的な知識と経験が求められることも事実です。
不明な点や複雑なケースについては、障害年金を専門とする社会保険労務士にご相談いただくことをお勧めいたします。適切なサポートにより、皆様が必要な支援を受けられるよう願っております。
投稿者プロフィール

- Ray社労士オフィス 代表 社会保険労務士
-
私には身体障害者手帳と療育手帳を持つ子どもがおり、障害者手帳を受け取った際の悩みや不安、孤独感を今でも鮮明に覚えています。
複雑な日本の社会保障制度の中でも、特に専門性を必要とするのが障害年金です。
この経験と社会保険労務士としての知識や経験を活かし、「同じ悩みを抱える方々の一筋の光となりたい」という強い想いのもと、Ray社労士オフィスを立ち上げました。
障害年金申請のサポートはもちろん、皆様の言葉に耳を傾け、心配事や将来の不安を解消し、安心して暮らせる明日を築くお手伝いをいたします。どうぞお気軽にご相談ください。
最新の投稿
- 10月 11, 2025面談コラム働ける脳出血でも障害年金は対象?|小脳出血による麻痺での相談事例(厚生年金加入中)
- 9月 23, 2025面談コラム潰瘍性大腸炎で障害年金はもらえる?|50代男性の相談事例(障害厚生年金3級の可能性)
- 8月 25, 2025面談コラム【特発性大腿骨頭壊死で歩行困難】人工関節の手術後も悪化した方からのご相談(石川県)
- 8月 18, 2025面談コラム【障害年金】脳出血による左半身に麻痺が残ってしまった方からのご相談(石川県金沢市)
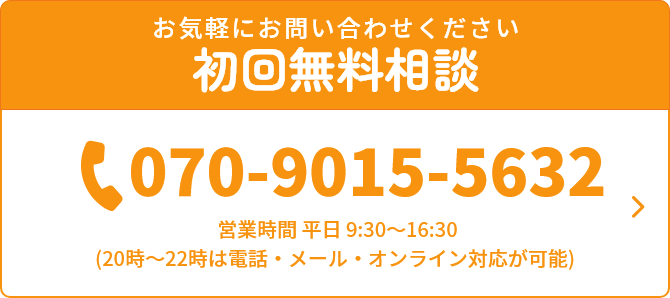


 初めての方へ
初めての方へ