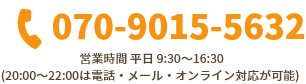【最新版】人工関節で障害年金はもらえる?|条件と申請ポイントを詳しく解説
目次
はじめに
人工関節の手術を受けた方やその家族の方から「人工関節を入れた場合、障害年金は受給できるのか」というご相談を数多くいただきます。人工関節による障害年金申請は、他の疾患とは異なる特殊な取り扱いがあるため、正確な知識が必要です。
人工関節の挿入置換については原則、障害等級3級に該当しますが、初診日の加入制度によって受給の可否が大きく左右されます。また、国民年金加入者であっても受給できる例外的なケースも存在します。
本記事では、社会保険労務士として多数の障害年金申請に携わってきた経験をもとに、人工関節における障害年金の受給条件と申請のポイントについて詳しく解説いたします。
人工関節(人工骨頭)を入れる場合は障害等級3級に該当する
人工関節を挿入した場合の障害等級について、国民年金・厚生年金保険障害認定基準では明確に定められています。
人工関節や人工頭骨を入れる場合には、あらかじめ障害等級が決まっているのが特徴です。人工関節(人工骨頭を含む)を挿入置換した場合、原則として障害等級3級の9号「身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するもの」に該当します。
この認定は、人工関節の挿入部位や種類に関わらず適用されます。具体的には以下のような場合が該当します。
- 人工股関節
- 人工膝関節
- 人工肩関節
- 人工足関節
- 人工骨頭(大腿骨頭など)
重要な点として、症状の重さや日常生活へ与える影響を総合的に考慮して、個別に障害等級が判定されるような障害もありますが、人工関節や人工頭骨を入れる場合には、あらかじめ障害等級が決まっていることです。これは他の障害とは異なる特徴的な取り扱いといえます。
ただし、障害等級3級に該当する場合には、障害厚生年金を受給できる方しか支給対象になりません。この理由を理解するために、障害年金の基本的な仕組みを確認しましょう。
障害年金とは?
障害年金は原則、公的年金に加入している人が病気やケガを原因として、障害により働けなくなったり仕事に制限を受けるようなときに支給される年金です。
障害年金には「障害基礎年金」と「障害厚生年金」の2種類があり、初診日にどの年金制度に加入していたかによって受給できる年金が決まります。
障害基礎年金は、初診日に原則国民年金に加入している方がもらえる障害年金です。自営業者やフリーランス、無職の方などが対象者です。また第3号被保険者である専業主婦や、20歳前に傷病を負った方も障害基礎年金の支給対象に該当します。
一方、障害厚生年金は初診日に厚生年金に加入している方を支給対象とした年金です。つまり初診日の時点で、会社員や公務員だった人が支給対象に該当します。
障害厚生年金は障害基礎年金に比べて支給対象の範囲が広い
障害厚生年金と障害基礎年金の大きな違いは、支給される障害等級の範囲です。
障害厚生年金の対象者は、全ての障害等級において障害年金が支給されるのに対し、障害基礎年金の対象者が支給されるのは障害等級1級と2級のみです。
| 障害等級 | 障害基礎年金 | 障害厚生年金 |
|---|---|---|
| 1級 | ○ | ○ |
| 2級 | ○ | ○ |
| 3級 | × | ○ |
| 障害手当金 | × | ○ |
よって原則障害等級3級に認定される「人工関節・人工頭骨の挿入置換」で障害年金を申請する場合については、障害厚生年金を受給できる方しか支給対象になりません。
なお、障害手当金とは、障害等級3級に該当する状態よりも軽い障害が残った場合に一時金のかたちで受け取れる制度です。
障害年金における3つの受給要件
受給要件は障害の種類や重さを問わず、障害年金を受給するために満たす必要がある条件を指します。
障害年金を受給するためには、以下の3つの要件をすべて満たす必要があります。
- 初診日要件
- 保険料納付要件
- 障害状態該当要件
初診日要件
初診日とは障害の原因になった傷病で、初めて医師等の診察を受けた日のことです。障害年金を受け取るためには「初診日に原則公的年金に加入している」必要があります。
初診日の確認は障害年金申請において最も重要な要素の一つです。初診日によって適用される年金制度が決まり、それに伴って受給できる障害等級の範囲も変わります。
もし公的年金に加入していなかった場合は、障害年金を受給できません。ただし20歳未満の方と60歳以上65歳未満で日本国内に在住されている方は、そもそも公的年金の加入義務がありません。初診日に公的年金制度に加入していなくとも、障害年金が支給される場合があります。
初診日の証明には「受診状況等証明書」が必要となりますが、医療機関の廃院やカルテの保存期間経過により証明書が取得できない場合もあります。そのような場合は、参考資料による初診日の推定を行うことになります。
保険料納付要件
保険料納付要件は、障害年金を受給するための保険料納付状況の基準です。具体的な内容は以下のとおりです。
初診日の前日において、初診日のある月の前々月までの期間において、3分の2以上保険料を納付または免除されていること。初診日が令和8年4月1日前にある場合については、初診日において65歳未満であり、初診日の前日において、初診日のある月の前々月までの一年間に保険料の未納がないこと。
上記のうち、いずれかを満たす必要があります。特例納付期限内であれば、申請前に保険料を納付することも可能です。
障害状態該当要件
障害年金を受給するためには、障害認定日時点の障害の状態が障害等級に該当する程度である必要があります。障害認定日とは、原則初診日から1年6ヶ月経過した日を指します。
人工関節の場合、前述のとおり原則として3級に認定されるため、多くの場合、障害基礎年金の受給者は障害年金を受給できません。
人工関節挿入置換における障害認定日の特例
通常、障害認定日は初診日から1年6月を経過した日とされていますが、人工関節を挿入置換した場合は特例が適用されます。
初診日から1年6ヶ月経過前に人工関節挿入置換の手術を行った場合には、手術を行った日が障害認定日と認められ、通常より早く障害年金を受給できる場合があるのです。
このように障害認定の特例が適用されれば、他の傷病で申請する場合と比較して早期に障害年金の請求を行えます。
この特例により、手術日以降速やかに障害年金の申請を行うことが可能となります。
初診日に国民年金の加入者であっても障害年金を受給できるケース
これまでに解説したように人工関節や人工頭骨を入れる場合には、原則障害認定3級に該当します。この場合、初診日に国民年金に該当する場合には、障害年金の受給対象にはなりません。
しかし、初診日に国民年金に加入している場合であっても、人工関節や人工頭骨の挿入置換を受けた方が障害年金の受給対象になるケースがあります。
社会的治癒が認められるケース
社会的治癒とは医学的にみて傷病が治癒していなくても、症状が安定していたり、自覚症状や他覚症状がなかったり、普通に生活や就労ができていたりする時期が一定期間あるような状態です。
社会的治癒に該当する場合には文字通りに治癒したとみなされます。その後、再び悪化するなどして医師等の診療を最初に受けた日が、初診日として扱われることになります。
具体例として、学生時代に膝の靭帯損傷で国民年金加入中に治療を受けた後、症状が安定して数年間治療を受けずに社会生活を送っていたところ、会社員となって厚生年金加入中に膝の状態が悪化し、最終的に人工関節の手術を受けた場合などが該当する可能性があります。
初診日に国民年金に加入していたとしても、新たに初診日と認められる日に厚生年金に加入している場合には、障害等級3級であっても障害年金の受給対象になる可能性があります。
ただし社会的治癒を主張するためには、申請に際して綿密な準備が必要です。社会的治癒に該当するかどうかは、診断書や病歴・就労状況等申立書など障害年金請求の際に必要となる書類の内容によって個別に判断されます。
社会的治癒の立証には以下のような要素が重要です:
- 一定期間(通常7年以上)の無治療期間
- その間の就労状況や日常生活の状況
- 症状の安定性を示す医学的根拠
- 再発時の症状の明確な悪化
障害等級2級以上に該当するケース
これまで解説してきたように人工関節や人工骨頭を挿入置換された場合には原則として障害等級3級に認定されます。しかし、場合によっては障害等級2級と認定され、初診日時点で国民年金に加入していた方でも、障害年金を受給できる可能性があります。
障害認定基準では、人工関節・人工骨頭の挿入置換について以下のような記載があります。
“一下肢の 3 大関節中 1 関節以上に人工骨頭又は人工関節をそう入置換 したものや両下肢の 3 大関節中 1 関節以上にそれぞれ人工骨頭又は人工 関節をそう入置換したものは 3 級と認定する。ただし、そう入置換してもなお、一下肢については「一下肢の用を 全く廃したもの」程度以上に該当するとき、両下肢については「両下肢 の機能に相当程度の障害を残すもの」程度以上に該当するときは、 さらに上位等級に認定する。”
主に下肢の大きな関節(股関節・膝関節・足関節)のうち2つ以上が機能を全く失う状態を指し、具体的には以下のケースにおいて、障害等級2級に該当する可能性があります。
- 関節が不適切な位置で固定され、動かなくなる状態
- 関節の動きが正常可動域の1/2以下に制限され、筋力が大幅に減少している状態
- 筋力が著しく低下または完全に失われている状態
- 膝関節のみの機能が失われた状態でも、結果として歩行が完全に不可能になっている状態
注意点として、上記のケースに当てはまれば必ず障害等級2級に該当するというわけではありません。人工関節を入れたあとの動作の制約が日常生活に与える影響が考慮されたうえで、総合的に障害等級が判定されることを押さえておきましょう。
障害年金の申請手続きの流れ
人工関節による障害年金の申請手続きは、以下の流れで進めます。
STEP1. 年金事務所で初回年金相談を受ける
まず、管轄の年金事務所で障害年金に関する相談を行います。初診日の確認、加入制度の確認、必要書類の説明を受けます。
STEP2. 初診日の確定
障害の原因となった病気やケガで初めて医師の診療を受けた日を確定します。受診状況等証明書の取得や、医療機関への照会を行います。
STEP3. 医師に診断書の作成を依頼する
人工関節挿入後3月以上経過した時点で、主治医に診断書(肢体の障害用)の作成を依頼します。診断書には人工関節の種類、挿入部位、手術日等の詳細な記載が必要です。
STEP4. 病歴・就労状況等申立書を作成する
発病から現在までの経過を時系列で整理し、受診の経緯、症状の推移、日常生活や就労への影響等を詳細に記載します。
STEP5. その他必要書類の収集
- 年金請求書
- 受診状況等証明書
- 住民票、戸籍謄本等
- その他参考資料
STEP6. 年金事務所等への提出
必要書類が揃ったら、住所地を管轄する年金事務所または市区町村の年金担当窓口に提出します。
STEP7. 審査・決定
提出から約3~4月後に、日本年金機構から年金証書または不支給決定通知書が送付されます。
初回無料相談実施中!
当事務所では、障害年金に関する初回相談を無料で実施しております。
人工関節による障害年金の申請は、一般的な障害年金申請とは異なる専門的な知識と経験が必要です。特に以下のような場合は、専門家にご相談いただくことをお勧めします。
- 初診日の証明が困難な場合
- 社会的治癒の可能性がある場合
- 複数の障害が併存している場合
- 過去に障害年金の申請で不支給となった経験がある場合
- 申請手続きに不安がある場合
障害年金制度の専門家である社会保険労務士へ相談すると、申請がスムーズになるためおすすめです。当事務所では、これまで多数の人工関節による障害年金申請をサポートしてまいりました。お一人お一人の状況に応じて、最適な申請方法をご提案いたします。
ご相談は完全予約制となっておりますので、まずはお電話またはメールにてお気軽にお問い合わせください。
おわりに
人工関節による障害年金は、適切な知識と準備があれば受給できる可能性の高い制度です。しかし、初診日の確定や必要書類の準備など、専門的な知識を要する部分も多くあります。
初診日に国民年金に加入している場合にも「初診日に国民年金に加入していたから無理かな」と、すぐに申請を諦めてしまうのではなく、受給の可能性を探ることをおすすめします。
たとえば症状の重さや日常の影響具合を考慮したときに、障害等級2級以上に該当するケースや、社会的治癒を活用して、厚生年金加入後の日を初診日に認めてもらえるケースもあるのです。
障害年金の申請は、一度不支給となってしまうと再申請が困難になる場合もあります。そのため、申請前の準備と正確な手続きが非常に重要です。
人工関節の手術を受けられた方やそのご家族の方で、障害年金の受給について疑問や不安をお持ちの方は、ぜひ専門家にご相談ください。適切なサポートにより、受給の可能性を最大限に高めることができます。
障害年金は、障害を持ちながらも社会で生活される方々の経済的な支えとなる重要な制度です。制度を正しく理解し、適切に活用していただくことで、より安心した生活を送っていただければと思います。
投稿者プロフィール

- Ray社労士オフィス 代表 社会保険労務士
-
私には身体障害者手帳と療育手帳を持つ子どもがおり、障害者手帳を受け取った際の悩みや不安、孤独感を今でも鮮明に覚えています。
複雑な日本の社会保障制度の中でも、特に専門性を必要とするのが障害年金です。
この経験と社会保険労務士としての知識や経験を活かし、「同じ悩みを抱える方々の一筋の光となりたい」という強い想いのもと、Ray社労士オフィスを立ち上げました。
障害年金申請のサポートはもちろん、皆様の言葉に耳を傾け、心配事や将来の不安を解消し、安心して暮らせる明日を築くお手伝いをいたします。どうぞお気軽にご相談ください。
最新の投稿
- 10月 11, 2025面談コラム働ける脳出血でも障害年金は対象?|小脳出血による麻痺での相談事例(厚生年金加入中)
- 9月 23, 2025面談コラム潰瘍性大腸炎で障害年金はもらえる?|50代男性の相談事例(障害厚生年金3級の可能性)
- 8月 25, 2025面談コラム【特発性大腿骨頭壊死で歩行困難】人工関節の手術後も悪化した方からのご相談(石川県)
- 8月 18, 2025面談コラム【障害年金】脳出血による左半身に麻痺が残ってしまった方からのご相談(石川県金沢市)
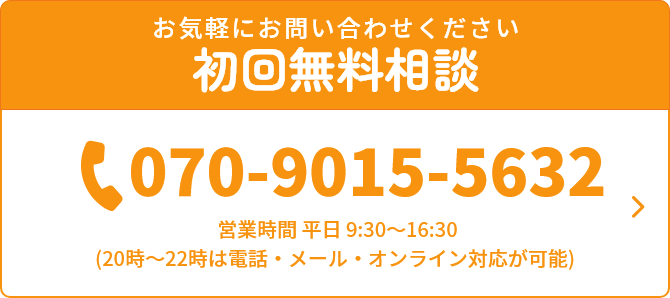


 初めての方へ
初めての方へ